J-クレジット購入者のメリットについて
2021/09/24
SDGsや脱炭素社会等、ここ数年の間で環境に対する取り組みが注目されてきております。今回ご紹介いたします「J-クレジット」もその中の1つです。
○J-クレジット制度について
Jクレジット制度とは太陽光発電設備や省エネ設備の導入、適切な森林管理などによって削減された温室効果ガスの「削減量」や「吸収量」を、J-クレジットとして国が認証する制度となっております。
そんなJ-クレジットは主に「創出者」と「購入者」に別れております。
今回は購入者にはどのようなメリットがあるのかご紹介いたします。
○J-クレジット購入者のメリットについて
1.環境貢献活動企業としてのアピールが可能
はじめにも触れた通り近年はSDGsや脱炭素社会といったような環境保全への動きが活発化しております。二酸化炭素や温室効果ガスの削減を目標に掲げている企業が多いですが、なかなか一社で達成するのは難しいと言われております。そこでJ-クレジットを購入することでしっかり温室効果ガスを削減しているという実績を得ることが可能となります。こうすることで環境に貢献しているとアピールすることが可能になるというわけです。
2.地球温暖化対策推進法や省エネ法の活用が可能
J-クレジットは地球温暖化対策推進法や省エネ法の報告などにも活用することが可能です。
3.カーボンオフセットによるサービスの差別化
まず、カーボンオフセットについて、こちらはあくまでも排出量を抑えるという前提の上に、ある場所で排出したCO2などの温室効果ガスを、別の場所で吸収・削減しようという考え方のことを言います。J-クレジットをこのカーボンオフセットに利用することで、ブランディングなどを通じてサービスの差別化を図ることが可能となります。
このようにJ-クレジットを購入することで環境保全に対する動きをアピールすることが可能となっております。企業のイメージアップに向けてJ-クレジット購入を検討してみてもいいかもしれません。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
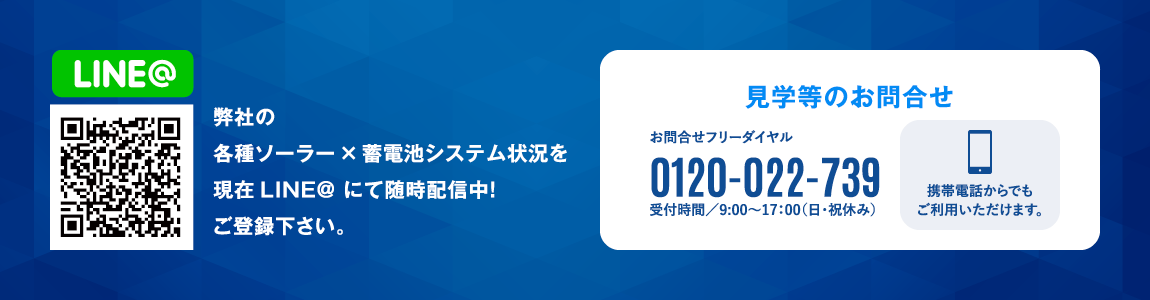
J-クレジット創出者のメリットについて
2021/08/26
太陽光発電設備や省エネ設備の導入、 適切な森林管理などによって削減された温室効果ガスの「削減量」や「吸収量」を国が承認する制度があることをご存知でしょうか?それが『J-クレジット制度』になります。このJクレジットはJ-クレジット創出者とJクレジット購入者によって成り立っております。今回はJ-クレジット創出者についてどのようなメリットがあるのかご紹介いたします。
○J-クレジット創出者とは??
まず、J-クレジット創出者とは何かについて触れていきましょう。
『J-クレジット創出者』とは、J-クレジットを生み出す中小企業、 農業者、森林所有者、地方自治体などのことをを指します。 J-クレジットを生み出すには、具体的に太陽光発電設備などの再生可能エネルギーの導入やLED照明などの省エネ性能に特化した設備の導入が挙げられます。
ではこのJ-クレジット創出者にはどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
○J-クレジット創出者のメリット
・J-クレジットの売却益を得ることができる
まず、このJ-クレジット創出者のメリットとしてJ-クレジットを売却することで、売却益を得らることができる点が挙げられます。この売却することで得た利益は、J-クレジット創出のための設備投資の一部に充てるなどして、 投資費用の早期回収や、さらなる設備投資に繋げることが可能です。
・ランニングコストの削減につながる
J-クレジットを創出するために、省エネ設備や自家消費型太陽光発電などの太陽光発電設備などを設置すると、 CO2などの温室効果ガスだけでなく、電気代などのエネルギーコストも削減することが可能です。 また、太陽光発電といった再生可能エネルギーの活用によって生み出される クリーンエネルギーを利用することにより、企業の環境経営にも貢献することができます。
また、上記以外でも地球温暖化対策に力を入れている企業ということをアピールすることが可能ですので企業のイメージアップにもつながります。J-クレジット創出者になるメリットは企業にとって大きなものとなると考えられます。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
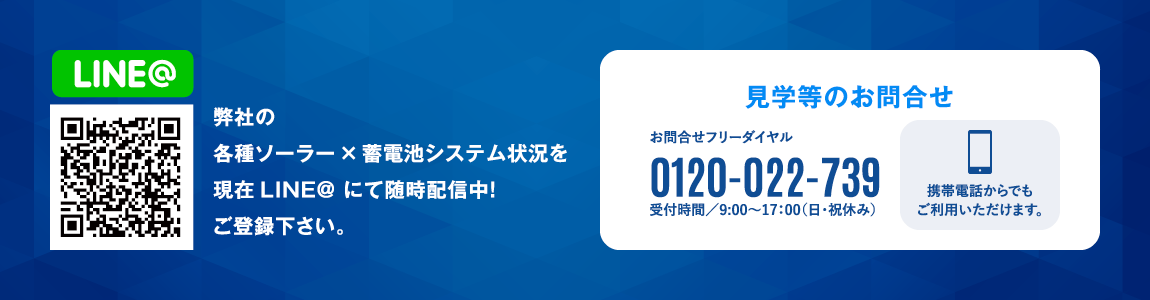
J-クレジット制度とは??
2021/08/26
みなさまは『J-クレジット制度』という制度についてはご存知でしょうか?このJ-クレジット制度とはCO2などの温室効果ガスの削減量や 吸収量を売買できるという制度となっております。 今回はJ-クレジットとは具体的にどのような制度なのかご紹介いたします。
○J-クレジット制度とは??
まず、J-クレジット制度とは太陽光発電設備や省エネ設備の導入、 適切な森林管理などによって削減された温室効果ガスの「削減量」や「吸収量」を、 「J-クレジット」として国が認証する制度となります。 この認証されたJ-クレジットは、大企業や中小企業、地方自治体などに売却することが可能となっております。
○J-クレジット創出者・購入者について
J-クレジット創出者・購入者について具体的に見ていきましょう。
■J-クレジット創出者とは?
『J-クレジット創出者』とは、J-クレジットを生み出す中小企業、 農業者、森林所有者、地方自治体などのことを指します。 J-クレジットを生み出すには、具体的に以下の方法がございます。
・太陽光発電設備など、再生可能エネルギーの導入
・LED照明など、省エネ性能にすぐれた設備の導入
■J-クレジット購入者とは?
『J-クレジット購入者』とは、上記のJ-クレジット創出者が生み出したJ-クレジットを購入する 大企業や中小企業、地方自治体などを指します。
このようにJ-クレジット創出者が生み出す『J-クレジット』をJ-クレジット購入者が購入するという仕組みが『J-クレジット制度』となっております。SDGsや脱炭素社会を目指す日本ではこのように環境に対する新しい動きが出てきつつあります。中小企業の方々はイメージアップにもつながりますので、ぜひこのJ-クレジット制度を利用してみてはいかがでしょうか?
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
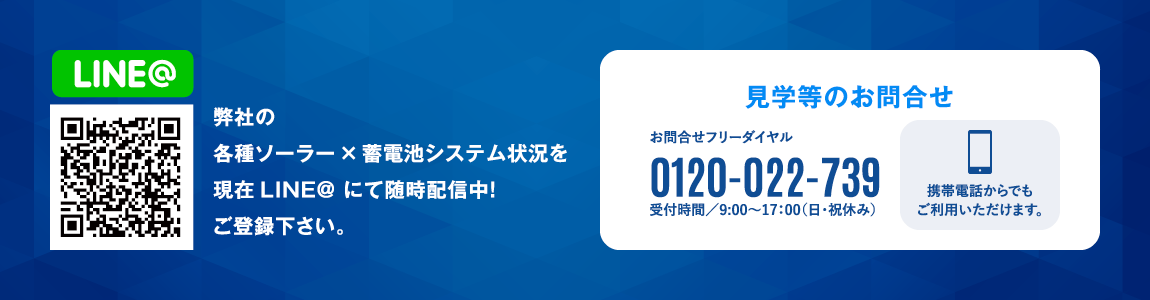
自家消費型で企業のBCP対策を!!
2021/08/25
ここ数年の間で地震や台風など自然災害による大きな影響が続いております。その際に問題として出てくるのが電力の問題です。2011年に起きた東日本大震災では電力の調達が困難となりそれ以降、BCP対策の取り組みが積極化してきました。今回は、災害時の電源確保が事業継続に与える影響と重要性と、非常時の電力調達方法として太陽光発電を取り入れるメリットとはあるのかご紹介いたします。
○BCP対策とは??
まず、BCP対策とは何か見ていきましょう。
BCPとは「Business Continuity Plan」の頭文字を取ったもので、日本語訳すると「事業継続計画」という意味になります。BCPは災害等で通常業務が継続できなくなることをできるだけ避けるために、災害などが発生した場合に損害を最小限にとどめ、早期に復旧し事業を継続するためには、どのような対応をとるかを予め計画しておくものとなっております。
災害時の事業継続における重要な要素として「電力確保」が挙げられます。これまでに受けた災害でも電力供給ストップから復旧までに1週間かかることがございますのでまだまだ課題は多いです。
緊急でできる停電対策として、「無停電電源装置(UPS)」や「蓄電池」がございますが、蓄電池は蓄電池自体には発電性能はございませんので、電力を使い果たしてしまえば、電力不足になってしまいます。想定外の災害に備え、停電した場合に、「業務にどのくらいの電力量が必要なのか」「停電したらどのような影響が出てくるのか」など対策を講じる必要があります。
○BCP対策は自家消費がおすすめ!
太陽光発電は火が照っている時間帯であれば発電が可能です。「太陽光発電設備」と「蓄電池」を導入することで、BCP対策だけでなく、平時であっても自家消費により電気代削減ができることや、遮熱効果があること、企業の環境価値向上など様々なメリットがございます。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
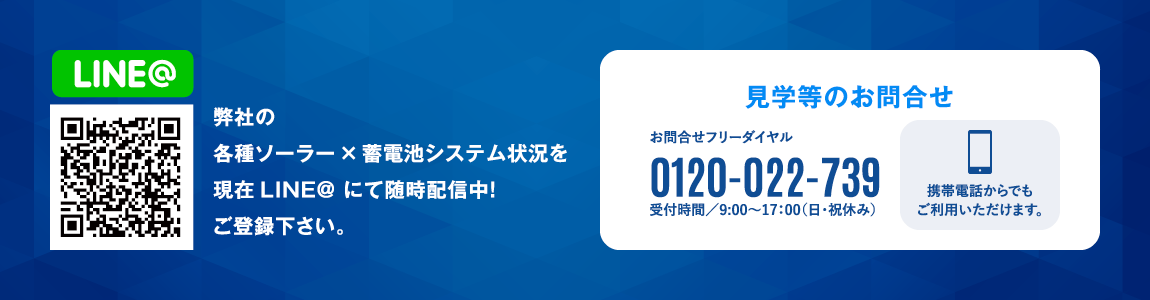
企業が自己託送を導入するのはアリかナシか!?
2021/08/18
ここ数年で「自家消費型」の太陽光発電が注目されてきております。ですが、所持している土地の広さや日当たり等が十分でない場合は設置が難しい場合がございます。そんな時は「自己託送制度」を利用することで自家発電型の太陽光発電を利用することが可能になります。
まず、そんな自己託送制度のメリットとデメリットについて触れていこうと思います。
○自己託送のメリットとデメリット
メリット:
1.電力コストを抑えることができる
まず、自己託送のメリットとして大きいのが、会社全体の電力の自家消費量を増やすことで、電力コストを抑えることができる可能性がございます。FIT買取期間終了後も自己託送に切り替えることで節電につなげることができますので、これは大きなメリットと言えるでしょう。
2.CO2の削減に貢献できる
太陽光発電は発電中に温室効果ガスを排出しないので、環境問題の改善にも貢献することが可能です。つまり、どういうことかというと、自社の電力を太陽光発電で賄うことでCO2の削減に貢献できSDGs事業にも取り組むことで、企業のイメージアップにつなげることが可能となります。最近ではESG投資も出てきましたので、企業の価値を上げる意味でも導入のメリットはあるといえます。
デメリット:
1.送電料金の発生
自己託送の送電サービス料金は二部料金または完全従量料金からの選択制となっておりますので、この点はしっかり確認しておく必要がございます。
2.負荷変動対応電力料金
電力会社の送配電ネットワークを利用するには、送電する電力量を事前に決めておく必要があり、もし送電量が不足した場合は「負荷変動対応電力料金」という一種のペナルティを支払わなければなりません。ですので、ある程度計画を立てて取り組む必要があるといえます。
このように自己託送にはメリットとデメリットそれぞれあることがわかります。
○企業が自己託送を導入するのはアリかナシか!?
上記のように自己託送には送電料金の発生や送電量が不足した際のペナルティがあるといったデメリットも存在しますが、企業が再生可能エネルギー事業を行っているとイメージアップに繋がりやすくなるのではないでしょうか。もし、自分の土地に発電条件が揃っていない場合は自己託送制度を導入するのはアリだと考えられます。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
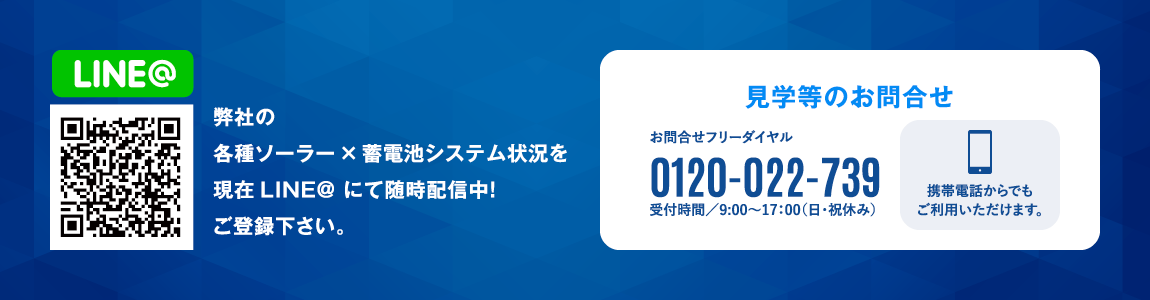

 kk-muraoka.com
kk-muraoka.com