なぜBCP対策が必要になるのか??
2022/01/02
近年起きた大震災により、事業継続が困難になってしまったというケースが実際にございます。中小企業では特にこの備えができていないところが多いので緊急時に対応できないという企業がまだまだ多い印象です。
○BCP対策について
そんな、緊急時に対応できるように備えておきたいのがBCP対策です。BCP対策とは自然災害などの緊急事態発生時に事業を継続するため、もしくは事業が停止した場合に一刻も早い復旧をするための計画、およびマニュアルそのものを指します。
○そもそもなぜBCP対策が必要になるのか?
数十年このような被害にあう機会がない場合、BCP対策の必要性を感じない企業も中にはあるかもしれません。ですが、そんな企業でもBCP対策は行ったほうがいいでしょう。というのも、災害など緊急時は、初動対応のスピードと内容が肝心だといわれています。自然災害などの緊急事態に対する準備不足は、人的被害やインフラ機能の停止につながってしまう可能性がございます。従業員を守り、事業を継続させることで顧客をも守ることは企業の責務と言えるでしょう。そのためにもBCP対策は必要と言えます。
また、BCP対策を立てることで、自社の業務における重要度・優先度」「自社の強み・弱み」が明確になりますので、事業を見直すきっかけにもなります。
緊急事態が起きてから対策するとなると実際は間に合いませんし、緊急時に落ち着いて行動するということも容易なことではありませんので、事前にどのような被害が起きた場合どのような動きをしていくのかというところをBCPを通して考えていく必要があります。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
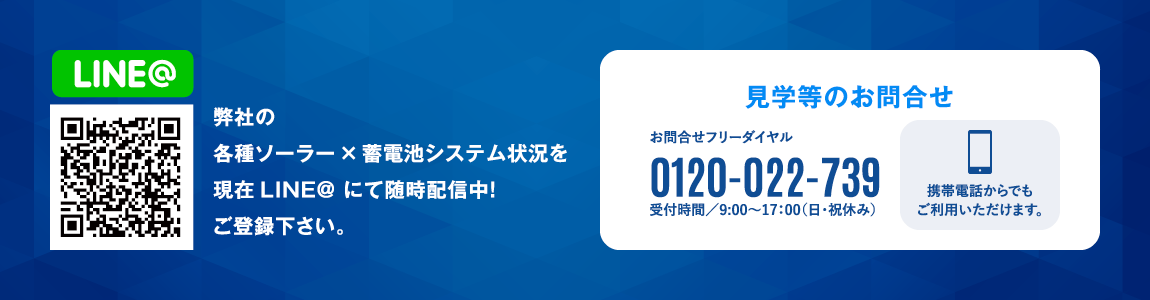
BCPを策定するための4つの手順
2022/01/01
皆さまは常日頃緊急時の備えはしておりますか?日本では、ここ数年の間に地震や洪水が増え、最近では火山活動による影響も想定されてきております。もし、自然災害による被害を受けてしまったらどのような行動を取るか、それがBCP対策です。
○BCP対策とは?
事業継続計画(BCP)とは、自然災害などの緊急事態発生時に事業を継続するため、もしくは事業が停止した場合に一刻も早い復旧をするための計画、およびマニュアルそのものを指します
ですが、実際に被害に関する想定というのは難しいです。そこで今回はBCPを策定する4つの手順をご紹介いたします。
○BCPを策定するための4つの手順
1.プロジェクトチームの編成
自社の各部門から人員を招集し、プロジェクトチームを編成して進めていきます。
2.優先する中核事業を選定する
中核事業(会社の存続にかかわる最も重要性の高い事業)を選定します。重要である事業をいくつか選定し、その中から優先順位を決めていきます。この順位の決め方としてのポイントは「重要度」と「頻度」です。事業がストップしてしまった場合にどのくらいの損失が出てしまうのかを判断し決めていきます。
3.中核事業が受ける被害を想定する
緊急時に上記で選定した中核事業がどの程度の影響を受けるのかを検討していきます。中核事業に関連する部門所在地における自然災害の発生率を調査し、災害によって中核事業や経営資源がどれ位の影響を受け、事業継続にどの程度支障を及ぼすのかを想定しておきます。 また被害を受けた際に、建物や設備の復旧にはどれ位の費用と時間が必要か、また復旧までの事業中断期間の損失はどの程度かも、あらかじめ分析しておくことが大事になってきます。
4.復旧への動きを決める
被害が発生してから復旧にあたる際に自社内で「どのように動き始めていくか」を想定していきます。どのような被害が発生したのか把握し、中核事業の継続に不足している“モノ”や“情報”を見極め、現状把握には、部署を超えた情報共有および協力体制を、有事において、迅速に行動を開始できる体制を整え、事業継続計画(BCP)にも明記しておくことが大切です。
このようにBCPを策定するためにはあらゆる被害のことを想定し、その後どのような行動をとっていくか考えていく必要がございます。
SDGs:気候変動問題とそのターゲット
2021/12/06
みなさまご存知のことかと思いますが、数年前から気候変動について問題視されてきております。2015年に国連にて採択されましたSDGsの13つ目の目標にも「気候変動に具体的な対策を」ということでこの問題に対して具体的な取り組みをしようという流れに現在でもなっております。
この目標は以下の5つのターゲットからなりたっております。
・すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応の能力を強化する。
・気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。
・気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。
・重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国 のニーズに対応するため、2020年までにあらゆる供給源から年間1,000億ドルを共同で動員するという、UNFCCCの先進締約国によるコミットメント実施するとともに、可能な限り速やかに資本を投入して緑の気候基金を本格始動させる。
・後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や⻘年、地方及び社会的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する。
気候変動の人為的要因として考えられているのが二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスです。ですので、この気候変動の問題を解決するには日常で排出する二酸化炭素の量を削減していく必要がございます。その対策として、世界各国が再生可能エネルギーの導入に力を入れています。日本でも導入が進んでおり、導入実績は世界トップクラスと言われております。このように気候変動の問題を少しでも解決していくために今後再生可能エネルギーに期待をしていきたいですね。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
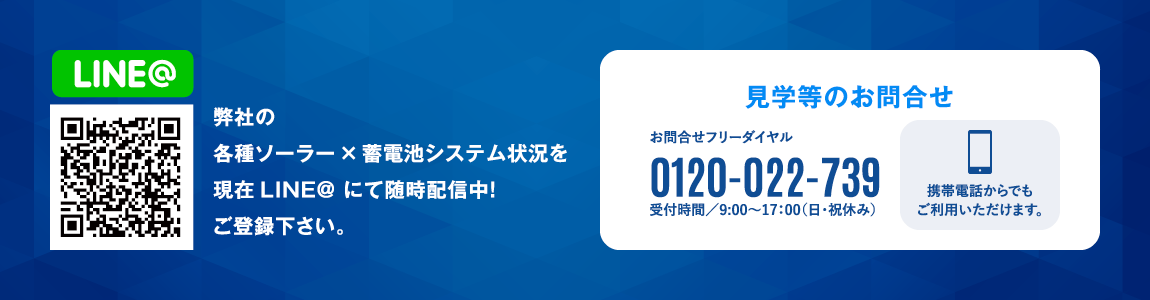
世界の電力問題とそれに私たちができること
2021/12/05
現在、私たちが当たり前に使用できている電気、世界でどのくらいの人が利用できているかご存知でしょうか。実は90%の人が利用できている状態だと言われております。残りの10%の人達は電気を利用することができていないということになります。サハラより南にございますアフリカや東南アジアでは多くの人々が電気のない暮らしを送っているのだそうです。中でも農村部ではエネルギー不足が深刻なため、電気のない暮らしを送る7.9億人のうち85%は農村で暮らす人々と言われております。
電気が使用できないことでどのような影響が出てしまうのでしょうか。
まず、産業発達ができないという問題がございます。現在、産業の発達において電気は必要不可欠なものとなっております。エネルギーが不足している地域・国の主な産業は、農産物や魚類を加工せずそのまま販売するという一次産業が主です。このような作物の加工や保存できる環境が整っていないということになってしまいますので、産業の発展も難しくなってしまいます。
次に電気が使用できないことで教育の問題が発生いたします。電気が使用できない国々では木を燃やすことで暖を取ったり明かりをつけるそうです。この木を取るのは主に女性か子どもの役目となっているようです。つまり、子どもに十分な教育をする時間を与えることができず将来安定した職業を手に入れることができず、結果的に貧困を生んでしまうのだそうです。
このように電気が使用できないことで多くの問題が出てきてしまいます。そのような問題を受けSDGsでは7つ目に「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」という目標が立てられました。
この目標に向けて私たち一人一人が意識して行動をすることで、こういった問題の解決へ近づいていくのではないでしょうか。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
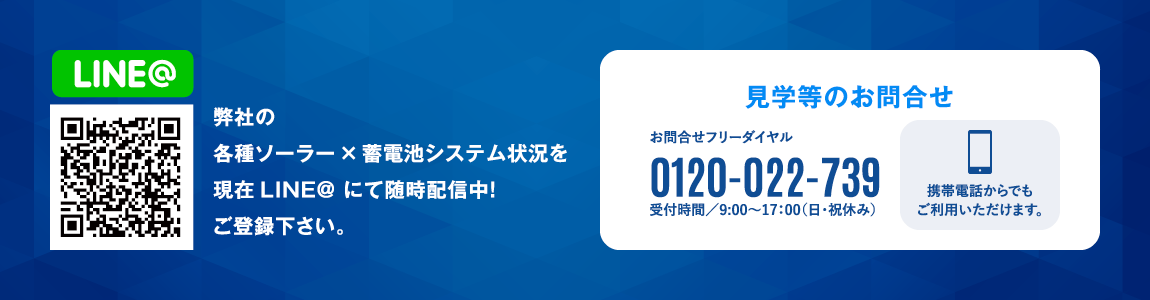
ESG投資の種類について
2021/12/04
財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮した投資としてESG投資がございます。気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや、企業の新たな収益創出の機会を評価するベンチマークとして、SDGsと合わせて注目されています。
そんなESG投資ですが、数種類ございます。今回はそれぞれのESG投資の種類についてみていきましょう。
・ネガティブスクリーニング
ネガティブスクリーニングとは、社会的または環境に対する基準を満たさない企業を排除することです。特定のESG基準に基づいてファンドやポートフォリオから基準に満たない一部のセクターや銘柄を除外します。ESG投資の主な方法はこのネガティブスクリーニングです。
・ポジティブスクリーニング
ポジティブスクリーニングとは、同業種の中でESGへの取り組みが高い企業に投資することです。ESGへの取り組み評価が高い企業は「中長期的に見て業績も高くなる」という発想に基づいて投資します。
・国際規範に基づくスクリーニング
国際規範に基づくスクリーニングとは、ESG分野の国際基準を満たしていない企業を投資対象リストから除外することです。
・ESGインテグレーション型
投資先を選定する際に意思決定のプロセスに財務情報だけでなくEnvironment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の非財務情報を組み込むことです。
・サステナビリティテーマ投資型
サステナビリティを全面的なテーマとしたファンドに投資することを指します。サステナビリティとは「環境」「社会」「経済」といった3つの観点から社会を持続可能にしていこうという考え方のことです。
以上一部ではございますが、ご紹介いたしました。ESG投資によって、企業の社会的評価の基準も大きく変わってきております。ビジネスを拡大されたいという方はこの「環境」「社会」「ガバナンス」を意識して動いていくことが今後大事になってくるでしょう。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
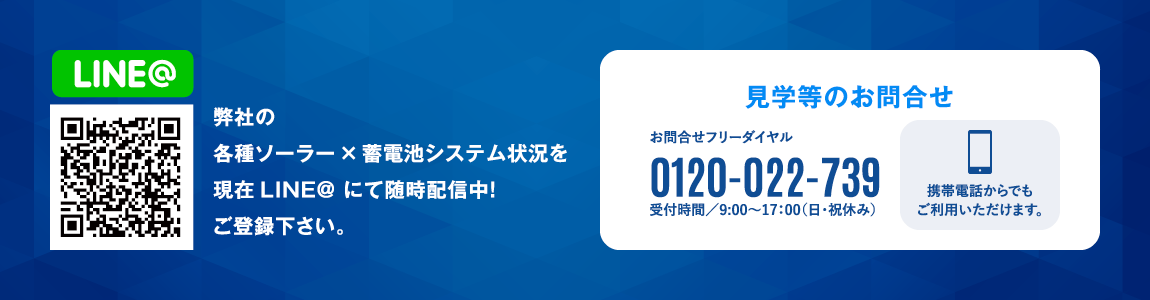

 kk-muraoka.com
kk-muraoka.com