SDGsウォッシュについて
2022/02/01
SDGsが世界的に注目を集めており、企業間においてもSDGsに関する動きをしているかしていないかで大きく評価が変わってくるようになって参りました。
ですが、近年その動きから「SDGsウォッシュ」が問題視されていることはご存知でしょうか?
まず、SDGsウォッシュとは何か見て行きましょう。
○SDGsウォッシュとは?
SDGsウォッシュとは、実態が伴っていないのにSDGsに取り組んでいるように見せかけている状態のことを指します。実際にはエコではないのにかかわらず、環境に配慮しているイメージを与えて消費者を誤解させるという意味を持つ「グリーンウォッシュ」という言葉がもとになってできた造語なのだそうです。
もし、このSDGsウォッシュが発覚するとどのような影響が出てきてしまうのでしょうか?
○SDGsが発覚することで想定される影響とは?
もし企業がSDGsウォッシュしていることが発覚した場合、やはり一番に批判をされてしまい、結果的にSDGsに全く貢献していない状態よりも企業の評価が下がる可能性が出てまいります。まず、SDGsの目的は、「貧困を終わらせ、地球を守り、地球上のすべての人々が平和と豊かさを享受することのできる社会を目指す」という多くの人が望んでいるところに向かうものでございますので、これに反することで多くの人から強い批判を浴びてしまうというわけです。
上記のようにSDGsの動きを少し間違ってしまうことで、SDGsウォッシュと指摘されてしまう可能性がございます。こうなることで企業にも大きな悪影響を与えてしまいますので、もし社内にSDGsの考えを取り入れる際はしっかりSDGsについて理解し計画を立てていく必要がございます。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
企業がBCP対策をするメリット
2022/01/06
大企業の間ではBCP対策が行われているところが多いですが、一方で中小企業ではBCP対策について行われていないところが多いというのが現状です。ではまず、このBCPについて軽くみていきましょう。
○BCPとは??
BCPとは事業継続計画(Business Continuity Plan)の頭文字を取った言葉になります。これは企業が、自然災害やテロ等により危機的状況下に置かれた場合でも、重要な業務が継続できる方策を用意し、生き延びることができるようにしておくための戦略を記述した計画書になります。
つまり、BCPを行うことで緊急時にどのような方法で事業復活まで進めていくかというところを明確化できるようになります。これは企業がBCP対策を行うメリットの1つとも言えます。
それでは他に企業がBCP対策をするメリットはどのようなものがあるのか実際にみていきましょう。
○企業がBCP対策をするメリットとは
・外部との通信手段の確保が可能になる
自然災害が発生した際に、従業員への安否確認や取引先への連絡をするために、外部と通信出来る手段を確保する必要があります。ですが、その災害の状況によっては停電が発生してしまうという可能性があり、その際は電力の使用ができませんので、携帯電話やノートPCが使用できたとしても充電ができないため通信手段の確保が困難になります。そこで、自社に太陽光発電設備を設置することで通信端末への電力供給や充電ができるようになり、社内や社外への連絡が可能になります。
・地域貢献につながる
自社で太陽光発電設備を設置することで、発電した電力を自社利用するだけでなく、近隣住民への提供も可能になります。停電が起きてしまうとエアコン等家電製品が全く使えなくなってしまいますので、体調を崩してしまう可能性も出てきます。そこで、災害発生時に地域住民を受け入れて電力を供給することで災害の被害に遭った方々を支援することが可能です。
このように企業がBCP対策を行うことで多くのメリットを得ることが可能です。また、BCPの策定によって中枢事業の見直しにも繋がりますのでその点においてもメリットと言えるでしょう。
BCP策定のの際に配慮したい機器とは?
2022/01/05
近年、大地震や噴火などさまざまな自然災害等が起きていることは周知のことかと思います。もし、その災害によって事業継続が困難になってしまったらどうしますか?いつどのような災害が起きてもおかしくはないので常に対策したいところです。そんな緊急時にどのような動きをするかということを策定するのがBCPになります。
○BCPとは??
BCPとは事業継続計画(Business Continuity Plan)の頭文字を取った言葉になります。これは企業が、自然災害やテロ等により危機的状況下に置かれた場合でも、重要な業務が継続できる方策を用意し、生き延びることができるようにしておくための戦略を記述した計画書になります。
このようにBCPを策定しておくことで、事業の継続のみならず、従業員の安全、災害後の取引先との連絡もできますので最低限の対処を行うことが可能です。
では、そのBCPを策定する上で配慮しておきたい機器とはいったい何があるのでしょうか?
今回は一部ではございますが、ご紹介いたします。
○BCP策定のの際に配慮したい機器とは?
1.照明
もし災害による停電が天候の悪い日や夜といった周りが見えづらい際に起きてしまった場合、避難経路の確保が困難になります。ですので、まず避難経路を確認し、緊急時に照明が必要な箇所を確認する必要が出てくるため照明は配慮しておきたいところです。
2.空調
もし真夏に災害による停電が起きてしまった場合、電源の確保ができない状態だと空調を使用することができません。この影響により熱中症などの体調による影響が出てくる可能性は高いと言えるでしょう。ですが、気をつけたい点として空調機器の消費電力は非常に大きいので使い方は十分考えておく必要があるでしょう。
3.エレベーター
急な災害により停電が起きてしまうと、エレベーターの中に閉じ込められてしまうリスクが出てきます。また、車椅子を使う方やベッドでの移動が必要な方の避難にはエレベーターは必須といえます。ですので、災害時にどのように電力を使用するかをしっかり考えておく必要があるでしょう。
以上、一部ではございますがご紹介いたしました。BCPではどのような場面でどのような被害にあったということを想定できる限り想定し策定を行うことが重要だと言われております。もしもの時に備えて企業で準備しておいて損はないでしょう。
BCP対策ができていない企業が多い理由とは?
2022/01/04
日本は近年巨大地震による被害も増えていることから分かる通り、自然災害が多い国ということもあり、常日頃緊急時に備えておく必要がございます。BCP対策もその1つです。
○BCP対策について
BCP対策とは、自然災害などの緊急事態発生時に事業を継続するため、もしくは事業が停止した場合に一刻も早い復旧をするための計画、およびマニュアルそのものを指します。
このBCP対策を行うことで、従業員安全の確保や事業の損害を最低限に抑えることが可能です。ですが、中小企業ではこのBCP対策を行なっていないところがほとんどです。なぜBCP対策を行なっていないのでしょうか。これにはさまざまな問題や導入に対する課題がございます。
○BCP対策の課題や問題点
■BCP対策の策定はコストが発生する
(BCP)を策定するには、詳細な下調べ、各部署からの人員の協力、顧客との協議、コンサルティングなどが必要になり、策定後にも、計画が実行できるようなコストの投入や従業員の教育が必要になります。当然これらには人件費が発生いたしますので、起きるか起こらないかわからない対策にコストをかけづらいという財政面での問題がございます。
■BCPが機能しない可能性
BCPを策定しても必ず想定された被害が来るというわけではありません。つまり、策定したBCPが現実には当てはまらないというリスクがありますので、できる限りさまざまな場面を想定しBCPは策定しておく必要があります。
以上のような問題点から、財政面的に人員の導入が難しいという企業がBCPの対策ができない理由の1つです。
ですが、最悪の場合を想定するとBCPの策定はしておいた方がいいでしょう。現状の利益より損害をいかに出さないかに費用を割いておくことで事業の継続が可能になります。ですので、BCPの策定は積極的に行った方がいいと考えられます。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
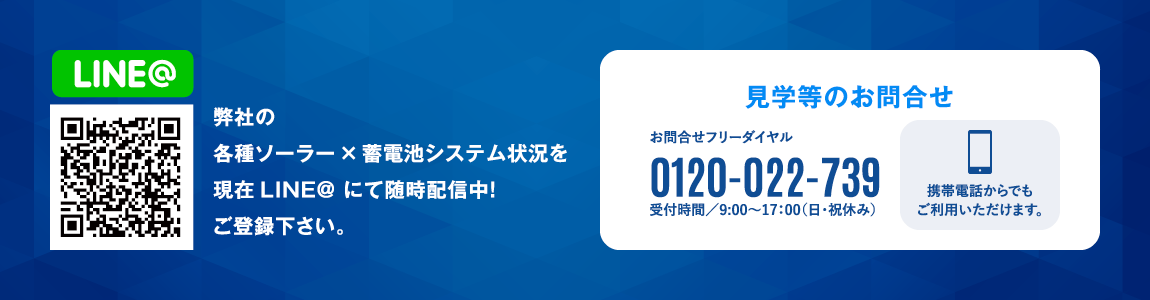
BCPを上手く機能させる4つのこととは?
2022/01/03
2011年に東日本大震災や2016年に起きた熊本地震のような自然災害で日本の多くの企業が損失を受け継続が困難になってしまう状態にまでなってしまいました。というのもBCP対策のような緊急時に備えた動きを策定していなかったところが多く、どのように動くべきかを計画立てていなかったというのが1つの要因だと言われております。ですが、BCPを策定すると言ってもなかなか専門性のある内容になってきますのでなかなか容易なことではございません。そこで今回はBCPを上手く機能させるにはどのようなところを注視していけばいいのかご紹介いたします。
○BCPを上手く機能させるには?
1.事業継続計画(BCP)対策の対象は中核事業に絞る
BCPの策定範囲は中核事業に絞る必要がございます。これは収益面の安定に直結しますので、中核事業を選定しその中でも優先順位を決め策定していく必要がございます。事業数の多い企業ほどBCPにおける選択や策定範囲の見極めが重要になってきます。
2.顧客と協議をして目標を定めておく
顧客とあらかじめ「緊急事態発生からどの程度の時間で、通常の何割程度まで事業を復旧すればよいか」を協議して、目標設定をおこなっておきます。そうすることで顧客の信頼を得ることができますし、計画を立てることで現場を混乱させることもありません。
3.具体的な動き方を明らかにする
BCPにまとめる緊急時の動き方は細かく明記しておく必要がございます。大まかな内容だといざ緊急時になった際に現場は混乱してしまいます。ですので、この災害が起きたらこのような動き方をすると言ったような具体的なところを明記することで、人為的な被害や事業の損害も可能な限り最低限に抑えることが可能です。
4.事業継続計画(BCP)対策に沿った対応訓練を実施する
BCPは策定するだけでは意味がありません。日々内容を周知することや、定期的な訓練や講習会を実施し、役職関係なく従業員の意識向上を図るようにします。
以上のことに注意しながらBCPの対策を行うことで事業の継続にもつながりますのでぜひ参考にされてみてください。

 kk-muraoka.com
kk-muraoka.com