オンライン代理制御とは?
2022/03/05
2022年に出力制御が大きく変わってくることが予想されます。というのも2022年の早期にオンライン代理出力制御の導入が検討されているということがあるためです。そこで今回はオンライン代理制御についてご紹介いたします。
○オンライン代理制御とは??
オンライン代理制御は経済的出力制御とも呼ばれております。これは、オフライン事業者が行うべき出力制御を、オンライン事業者が代理で実施、代理制御の対価を受け取るというものになります。
オンライン事業者にはオフライン事業者の代わりに制御した時間帯に発電していたであろう「みなし発電量」に、FIT買取価格を乗じた金額が、代理制御の対価として支払われ、
オフライン事業者にはオンライン事業者に代わりに制御をしてもらうことから、本来出力制御されるはずであった時間帯の発電量について、買取義務者から対価が支払われないこととなります。
■それでは、オンライン代理制御を行うことでどのような効果が出るのでしょうか?
まず、上記にもありますが、オフライン事業者は、電力会社から前日に出力制御の連絡を受けて、発電事業者側で現地操作で停止したり復帰させたりして制御を行うのでオフライン事業者にとっては手動制御の手間が省けます。
そして、オンライン代理制御を行うことで、実需給に近い柔軟な調整が可能になるため、今までの出力制御と比べて負担の軽減が期待されます。
このようにオンライン代理制御を行うことで、出力制御に対する考え方も変わってくると考えられます。今年導入予定とのことですので、オンライン代理制御についてしっかり確認しておきましょう。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
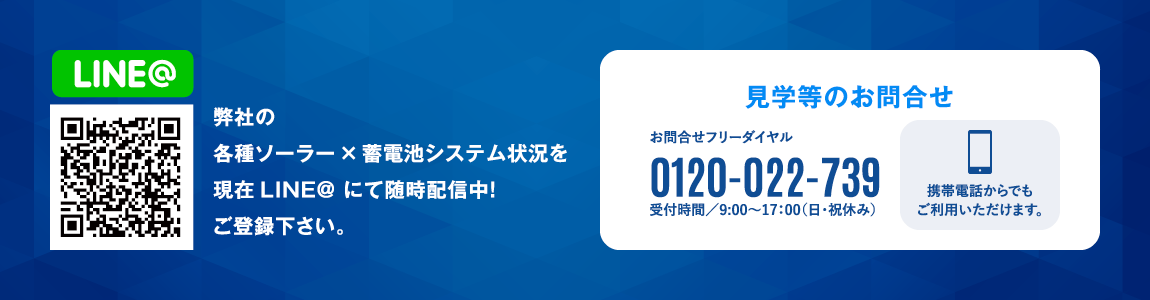
FIPに移行するメリットとデメリット
2022/03/04
今度の4月から本格的にFIP制度が導入されます。これまで太陽光発電ではFIT(固定価格買取制度)での運用がメジャーであったため、FIPに移ることでどのようなメリットが出てくるのでしょうか?
○FIP制度に移行することによるメリットとは?
・電力需要の高い時間帯を狙って売電できる
FIP制度では電力需要の高い時間帯は、買取価格も上昇するため、電力需要の高い時間帯に合わせて売電を行うことができれば、効率的に売電収入の確保を目指すことができます。
・アグリゲーションビジネスの展開ができる
FIP制度が導入されることでアグリゲーションビジネスが期待されております。アグリゲーションビジネスとは、小規模かつ複数の再生可能エネルギー発電事業者から発電された電気を束ねて随時調整しながら、電力の需要と供給を管理する事業のことをいいます。日本国内ではまだ未発展であるため、電力需給に合わせて送配電をコントロールできる事業者の存在価値は高まります。
このようにFIP制度に移行することで上記のようなメリットが期待されています。対してデメリットについて見ていきます。
○FIP制度に移行することによるデメリットとは?
・電力需要の低い時間帯に売電を行うと収益が下がる
メリットのところでもご説明した通り、売電を行う時間帯は重要になってきます。電力需要の高い時間帯で売電を行えば高い買取価格で売電ができますが、対して電力需要の低い時間帯に売電をすると収益の低下が想定されます。
・収益の見通しが立てづらい
FITは固定価格の買取であったため収益の見通しが立てやすいというのがメリットでした。対して、FIPは市場価格やその他要因によって買取価格が変わってきますので、収益の見通しは立てづらいと言えます。
このようにFIPに移行する上でメリットとデメリットは出てまいります。
しっかり、自分にあったものであるかを見極めFIPの導入を検討されてみてはいかがでしょうか?
アグリゲーションビジネスについて
2022/03/03
2022年の4月よりFIPが始まるということで「アグリゲーションビジネス」に注目が集まっております。ではなぜ、このアグリゲーションビジネスに注目が集まっているのでしょうか。
○アグリゲーションビジネスに注目が集まった背景
やはり、この理由として大きいのはFIP制度の導入です。FIP制度には、プレミアムの上乗せやバランシングコストなどの手当も考慮されておりますので、これらをインセンティブにして、再エネ事業者のみならず、更なる再エネ導入が進むことが期待されております。このうちの1つが「アグリゲーションビジネス」です。
FIPの電力市場において、最適な売電計画を実行する「再エネアグリゲーター」の存在は必要不可欠となってきます。
○アグリゲーター
アグリゲーターは「アグリゲート(aggregate)」からきており、英語で「集める」や「合計する」「総計する」などの意味で、「アグリゲーター」とは「集める人・物・組織」のことを意味します。再エネの分野においては分散型電源等の電気を集めて需要家に供給を行う「特定卸供給事業者」や「小売電気事業者」が想定されています。
4月からのFIP導入に合わせてアグリゲータービジネスも可能であれば検討してみるのもいいかもしれませんね。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
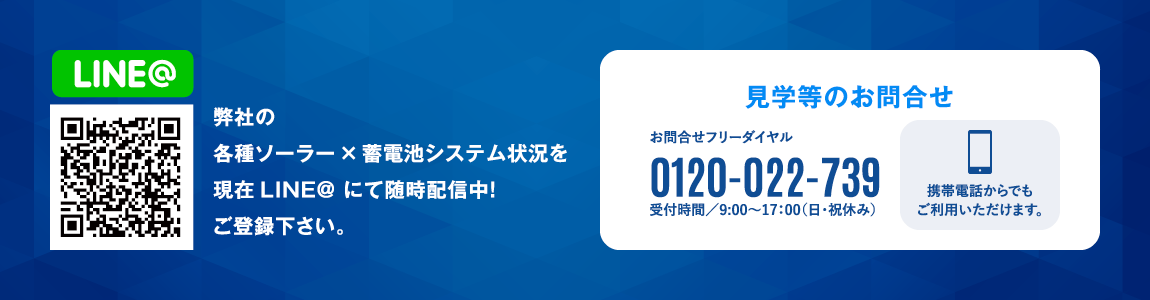
FITとFIPの違いについて
2022/03/02
2012年に再生可能エネルギー発電の普及のためにFIT制度(固定価格買取制度)が導入されました。その狙いの通り導入後再生可能エネルギー発電所は爆発的に増えたのですが、賦課金による国民への負担も出てき始め、今年4月にFIP制度が始まります。そこで今回はFIPとFITの違いについてご紹介いたします。
○FIT制度
FIT制度は前述の通り2012年に導入されました。FIT制度は発電した電力を電力会社が固定価格で買い取ってくれるというもので、その買取期間は20年ということもありましたので長期的な安定投資としても注目を集めておりました。
○FIP制度
FIP(Feed in Premium)制度とは、再生可能エネルギー発電事業者が発電した電気を卸電力取引市場や相対取引で売電をした場合に、基準価格(FIP価格)と市場価格の差額をプレミアム額として交付する制度になります。
以上が簡単ではございますが、FIT制度とFIP制度の説明になります。それではFIPとFITではどのような差があるのでしょうか。ご紹介いたします。
○FIPとFITの違いとは??
FIP制度は、FIT制度と制度発足の目的という点で大きく異なってきます。FIP制度は、再生可能エネルギー設備を所有している個人や企業に向けて、競争力を付けたり自立を促したりするのが目的であるのに対し、FIT制度は普及を目的とした制度でになりますので、火力発電など他の発電設備と異なり電力市場とは切り離されております。
他にも、FIT制度は固定価格に売電量を掛けた額が売電収入であったのに対し、FIP制度は電力市場に連動した変動価格で売電することになります。
このようにFITとFIPでは大きく異なってきます。FIP制度は4月より始まりますので、ご利用される場合はしっかり制度について把握しておくようにしておきましょう。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
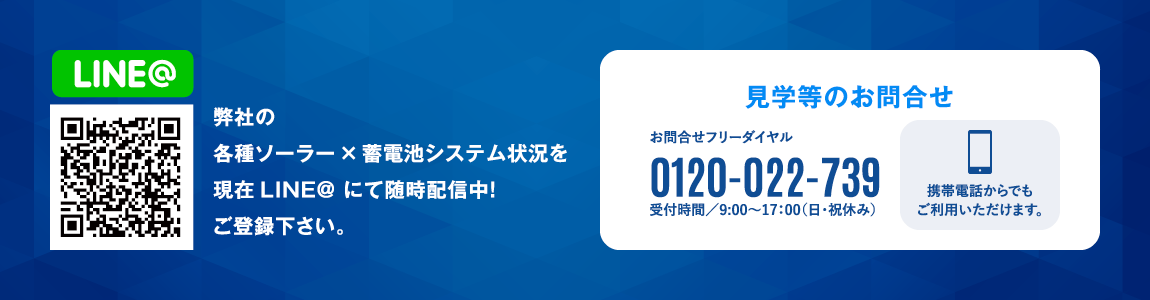
FIP制度について
2022/03/01
2022年4月より本格的にFIP制度が始まります。そこで今回はFIP制度とはどのようなシステムであるのかご紹介いたします。
○FIP制度について
FIP(Feed in Premium)制度とは、再生可能エネルギー発電事業者が発電した電気を卸電力取引市場や相対取引で売電をした場合に、基準価格(FIP価格)と市場価格の差額をプレミアム額として交付する制度になります。
FIP制度には主に3つの種類がございます。
詳細は以下の通りです。
1.プレミアム固定型FIP
電力卸市場価格に固定されたプレミアムを付与するもの
2,プレミアム固定型FIP(上限・下限付)
市場価格とプレミアムの和に上限と下限を設定したもの
3.プレミアム変動型FIP
電力卸市場の上下に応じて、付与するプレミアムが変動するもの。
になります。
FIPの主な収入はこのプレミアムになります。
FIP期間中固定の「基準価格」から、1ヶ月単位で算出される「参照価格」を引いた金額が「プレミアム単価」になります。
プレミアム単価=基準価格 - 参照価格
基準価格とは通常必要と想定される費用や適正な利潤などの事情を勘案して定められるもので、「FIP価格」とも呼ばれています。
参照価格は電気を市場取引によって売った場合に期待できる収入のことで、市場価格の平均価格を基礎として、1ヶ月毎に機械的に算定されます。
このFIP制度が2022年よりスタートいたしますので、利用される場合はしっかり学んで取り組むようにしていきましょう。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
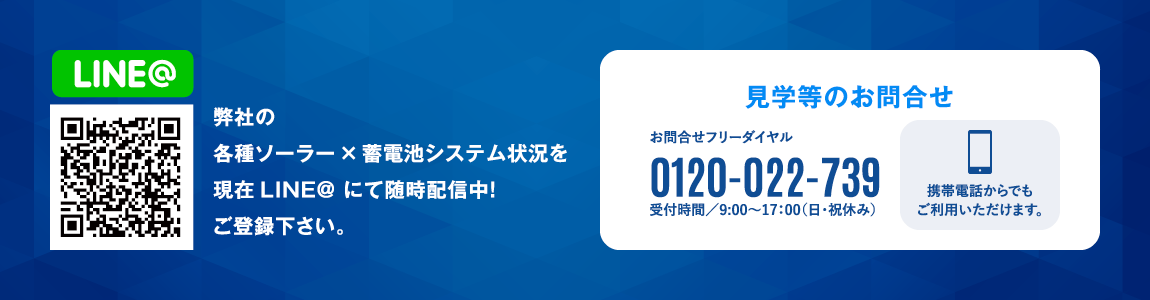

 kk-muraoka.com
kk-muraoka.com