太陽光パネル税のメリットとデメリット
2022/06/02
昨年12月に岡山県美作市で、事業用の太陽光発電パネルに課税する条例が制定され、総務省の同意を得て2023年度に全国初の導入を目指しております。
今回は太陽光パネル税を導入されると、どのようなメリットがあるのか、対してどのようなリスクがあるのかご紹介いたします。
太陽光パネル税のメリット
太陽光パネル税のメリットとして考えられるのは、災害リスクの多い土地への設備設置を抑制することができる点になるかと思います。
ですので、太陽光発電設備の周辺に住んでいる住民からすると大きなメリットであると捉えられるかもしれません。
○太陽光パネル税のデメリット
初めに申し上げますと、現在はデメリットが目立ってしまっている状況です。
特定の発電事業者に大きな負担が係る
太陽光パネル税は、出力10kW以上の事業用太陽光発電を運用している事業者や個人が対象になるため、固定資産税や消費税等に加えて太陽光パネル税を支払うことになり、かなり負担にかかってしまう税金になります。
この太陽光ぱねる税の使用用途は、防災対策や自然環境対策など、太陽光発電と関連性の少ないところにまで及んでおりますので、特定の負担者にとっては疑問点の多い政策であることはどうしても引っかかってしまいます。
再生可能エネルギーの普及をストップさせる要因となる
現在日本ではカーボンニュートラルやSDGsのような再生可能エネルギーの推進を広げておりますが、太陽光パネル税がもし導入されるとこの推進政策と矛盾してしまいます。もし、総務大臣が太陽光パネル税に同意した場合、今後全国的に自治体で類似の法定外目的税を提案する可能性が出てきます。そうなってしまうと税負担の増加や税の公平性を保つことが難しくなり、再生可能エネルギーの普及をストップさせてしまう要因になってしまう可能性がございます。
二重課税の可能性が出てくる
現在、太陽光発電の場合太陽光パネル等の設備や土地に固定資産税が発生しております。もし、太陽光パネル税が導入されたとなると、固定資産税と太陽光パネル税とで二重課税が発生してしまうのではという疑問点が出てきてしまいます。美作市の説明では、太陽光パネル税は売電行為に対する税金という解釈のようですが、これがもし可決されると税負担は莫大なものとなってしまう可能性がございます。
太陽光パネル税について
2022/06/01
昨年12月に岡山県美作市にて、事業用の太陽光発電パネルに課税する条例が制定されました。多くの事業者はこの条例に強く反対をしており、再生可能エネルギー普及拡大の動きに逆行するという声も上がっていることから、今後、総務省がどのような判断をするのか、注目が集まっております。
○太陽光パネル税について
太陽光パネル税は岡山県美作市の市議会で提案された条例案になります。この導入目的は、太陽光発電周辺の防災対策費用を確保するためとのこと。出力10kW以上の野立て太陽光発電などの設備が、太陽光パネル税の対象となっており、税負担は1㎡あたり50円の予定となっております。ですので、太陽光パネルの面積が広いほど、課税額の増加につながってしまうという仕組みになっております。この課税期間は5年間で、必要に応じて期間などが調整されております。
太陽光パネル税非課税になるには?
太陽光パネル税には非課税の件も設けられております。内容としては以下の通りです。
- 建築物の屋根などに設置された太陽光発電設備(野立て以外)
- 出力10kW未満の太陽光発電
- 出力50kW未満の太陽光発電でかつ砂防指定地や地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域に含まれない土地に設置されている
また、太陽光発電事業者が住民と円滑な関係を維持するための寄付金を出している場合は、寄付金相当額の税額控除(税額の20%を上限)という項目もあるようです。
さいごに
太陽光パネル税の概要については以上でございます。
もし、太陽光パネル税が導入されたとなると、事業者の負担はさらに大きくなってしまうことは間違いないでしょう。冒頭にも記してあります通り、この太陽光パネル税の有無は今後、総務大臣がどのような判断をするのかで大きく変わってきます。再生可能エネルギー関連の法定外目的税は国のエネルギー政策と変わってきますので、総務省だけでなく経済産業省との擦り合わせも必要になるので、国の判断も時間はかかってくるでしょう。
発電側課金によって収支の維持が難しい場合は?
2022/05/06
今回は、発電側課金案の課題はどのようなものが上がっているのか、もし発電側課金によって収支の維持が困難になってしまうことが想定される場合はどうすればいいのかご紹介させていただきます。
現在挙げられている発電側課金案の課題とは
発電側課金を行うことで、太陽光発電の維持管理費用負担が増加してしまうことが想定されます。
現在挙げられている発電側課金案は託送料金を中心とした費用負担に関する内容になるため、費用還元や補助金については想定されておりません。
ですので、発電側課金案の対象設備を所有している事業者にとっては、費用負担増加を前提とした運用を検討していく必要があります。
また、現在未定や仮の部分が多炒め、具体的に費用負担に対してどのように対処するべきか対策を決めることができません。
ですので、太陽光発電の事業者は、まずこの発電側課金による費用負担増かを前提として発電効率アップや維持管理費用の削減などといった対策に向けて準備するようにしたほうがいいと考えられております。
発電側課金によって収支の維持が難しい場合は??
発電側課金によって維持管理費用負担が増えてしまうことが想定されます。
ですので、これによる影響の対処方法についてはどのようなものがあるのでしょうか?
自家発電消費型に切り替える
収支維持が難しい場合は、全量自家発電消費型に切り替えて電気代の削減につなげるということも1つの手段としてございます。
全量自家発電に切り替えることで再エネ賦課金の負担も軽減されますので、多くの電気を使用される場合がこの方法を選んでみてもいいでしょう。
後付けで蓄電池を設置する
現在お持ちの太陽光発電システムに蓄電池がない場合、後付けで蓄電池を設置し、電気の効率的な消費や売電を図るのもいいと言われております。蓄電池を併用していれば、出力制御や余剰電力の発生時に電気を蓄えられますし、任意のタイミングで自家消費および売電することが可能です。
発電側課金で負担する割合について
2022/05/05
発電側課金の費用負担割合などについてどのようになっているのでしょうか。
1kWあたり1,800円の50% の案
2022年4月時点では、1kWあたり1,800円÷50%=900円を発電事業者が負担するという内容の案が出ておりました。
送電線の整備にかかる費用は、1kWにつき年間1,800円とされています。
有識者会議では、このことにより発電事業者の所有している発電設備1kWにつき900円の負担という案を作成しているそうです。
一部案件については例外か?
基本的には発電設備1kWにつき900円の負担で検討されているようなのですが、「住宅用太陽光発電」や「一部FIT認定済の太陽光発電」などは費用負担の除外対象として考えられております。
2015年6月以前にFIT認定を受けた太陽光発電は、利潤配慮機関という制度の対象となっております。FIT認定から3年間にかぎり高い固定買取価格で売電できる特別措置を受けることが可能です。また、発電側課金の対象設備として定められています。
対して、2015年7月以降にFIT認定を受けた太陽光発電は利潤配慮期間の対象外なので、発電側課金から除外される方向で検討されています。
住宅用太陽光発電とは?
出力10kW未満の太陽光発電のことを指します。住宅の屋根に取り付けられていたり、自宅のカーポートに設置されている太陽光発電が多いです。
このように太陽光発電設備は出力やFITの認定時期によって発電側課金の対象要件も変わる予定になっております。
以上が現在わかっている発電側負担の内容になります。
一部FIT物件はこの発電側負担が対象になると検討されております。その部分は発電事業者の方は把握をしておいた方がいいでしょう。
○村岡パートナーズでは3つの蓄電池施設を稼働予定です!!
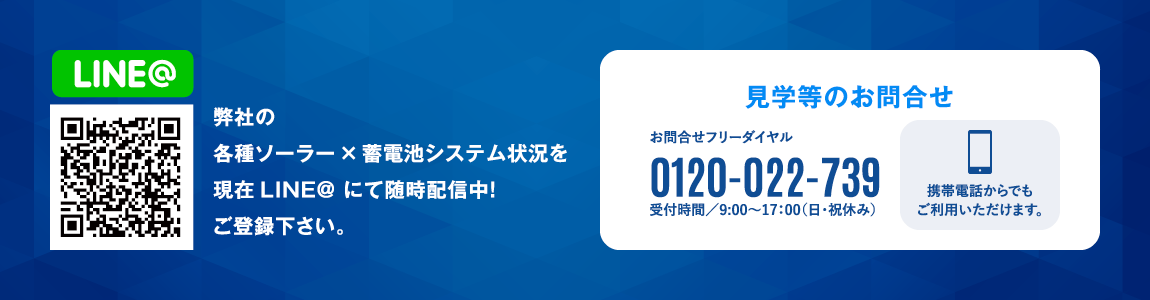
村岡パートナーズでは再生可能エネルギーの固定価格買取型である『FIT型』、遠隔地にある発電設備で発電した電気を自社施設で消費する『自己託送型』自社の発電設備で発電した電力を自社施設で消費する『自家消費型』の蓄電池施設を稼働予定です。
この『再生可能エネルギー×蓄電池システム』のシステム状況をLINEにて随時配信中ですのでぜひご登録ください。
発電側課金が2024年に実施か?
2022/05/04
経済産業省では再生可能エネルギーの制度として「発電側課金」を2024年に実施することを予定しているようです。
そこで今回は、発電側課金について現在わかっているところについてご紹介いたします。
○追加の経緯について
現在、託送にかかる料金は小売電気事業者が負担をしております。ですが、電力の需要は時代の進化とともに日々拡大し、送配電にかかる費用は増えてきております。このことより、送配電の費用負担について定めておく必要なのではないかといった考えが出てくるようになりました。現在の制度だと、送配電設備の増加要因を電気の利用者や電力供給によって利益を得る小売電気事業者と定められていますので、送配電にかかる費用は、小売電気事業者が全て負担しております。
ですが、この状況だと小売電気事業者が負担しきれない状況へ変化してきてしまっております。
費用回収不足
理由の1つ目として、費用回収不足の問題がございます。送配電にかかる託送料金は、全体の数割しか小売電気事業者から回収できていないため、赤字状態が続いてしまっているという状況です。
○託送料金を小売電気事業者で全て負担すべきという考え方
需要家や小売電気事業者が送配電設備の整備によって利益を得ているという考え方そのものがこの状況を産んでいると考えられております。ですので、新制度案で「再生可能エネルギー設備の急速な普及によって、太陽光発電事業者や風力発電事業者などといった再生可能エネルギー関連の発電事業者も、送配電設備の設置で利益を得ているのではないかという考え方」に切り替えることによって、発電事業をおこなっている企業が送配電設備の費用負担に関する義務を課すべきであるという案になっていきました。
経緯としては以上の通りです。
経済産業省を中心に議論が交わされ、発電者課金の実施に移ることになっております。今後、再生可能エネルギー事業を行う上でのランニングコストが大きく変わってくることが想定されます。これからどのように動いていくかによって発電事業者の負担が変わってきますので、しっかり確認しておきたいところではあります。

 kk-muraoka.com
kk-muraoka.com